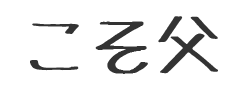戻ってきました。偏差値を信仰しない偏差値の考え方

ずっと本業の仕事が忙しくて、かつ子どもの部活がけっこういい線まで行ったりして、そちらにも時間をとられて、中学受験について考察したりできないでいました。でも、夏休みころになって、中学受験界隈のSNSからけっこう悲痛な声が聞こえてくるようになりました。
また、情報が十分でない保護者の方がけっこうあやまった知識で、無駄に心配したり右往左往しているようなケースも見受けられます。以前に書いた内容を少しアップデートして、書いてみようと思います。まずは偏差値です。
偏差値は絶対的な数値ではない
まず模試の偏差値は絶対的な数値ではない、というのが基本の考え方です。あくまでも受験者数の中の位置づけにすぎない、ということです。偏差値50が受験者の中の平均に相当する、ということです。
比較的学力が高い受験生が受けるSAPIXオープンの偏差値は、日能研や四谷大塚、首都模試よりも低く出ます。たとえば日能研(≒四谷大塚)の模試で偏差値50の成績だった場合、首都模試なら60くらいがでているかもしれません。でも、問題のレベルも範囲も違うので、そんなことを考えても意味がありません。
偏差値60の学校を志望校にしているから、常に偏差値が60である必要もありません。逆に偏差値60に届いているから安心というわけでもないのです。合格率が80%を超えていても必ず受かるわけではないですし。模試の合格率なんて、偏差値だけで出している数値なので、絶対的な数値ではないのです。そもそも合格率80%といっても10人中、2人は落ちるわけですから、安心できるわけないです。
模試の試験は入試とは内容が違う
四谷大塚の合不合判定テストで合格率が80%と毎回出ていても、実際の受験が安心とは限りません。合不合判定テストは年に6回ありますが、その6回で受験の範囲をすべて抑える設定になっています。つまりどこの学校にも対応できる平均的な問題をまんべんなく出しているだけですので、実際の入試問題とは異なります。
例えば実際の入試では、志望校でどの分野の問題がでるのかがポイントになります。算数の立体図形が苦手で、平面図形が得意な子がいたとします。その子の志望校で立体図形がでないならそれでOKです。模試で立体図形の単元がでて、配点も大きくて、それができないがために偏差値があまりよくなくても問題にはならないでしょう。
学校によっては特徴的な問題を出すところもありますので、学校の入試傾向を見て、それに合わせた対応ができればいいのです。ただ、特徴的な問題を出す学校を第1志望にしている場合、そこにあわせすぎると、第2志望や抑え校の対策に困ります。そういう意味ではある程度まんべんなく学習しておくというのは大切です。問題の傾向が似ているかどうかの詳しい状況は塾の先生と相談するのがいいでしょう。
じゃあ模試の偏差値は意味がないか?
結局のところ、入試で合格点が取れればいいわけで、模試でいくらいい偏差値を出していてもそれは模試にすぎません。模試の偏差値なんて目安にすぎませんから。とはいえ、模試で偏差値40しか出せない子が、偏差値65の学校に受かるかというと、それはかなり無理があります。
偏差値60以上の学校は、基礎学力があったうえで、さらにそのうえの思考力を求める問題が多いです。偏差値40だと基礎学力が定着していないので、そのうえの思考力というレベルには達していません。そういう意味では偏差値は参考にはなります。なりますが、絶対的な指針ではないので、一喜一憂しないことは大切です。
よく「持ち偏差値」という言葉をききますが、これは受験生の実力を示す偏差値のことで、一般的には9月以降の模試4回分の平均を出して、その偏差値が受験校の目安になるということです。
| 9月 | 52 |
| 10月 | 62 |
| 11月 | 54 |
| 12月 | 50 |
という偏差値の推移なら、52+62+54+50=218/4=54.5
54.5が持ち偏差値となります。十分な対策が可能なら、偏差値が10くらい高い学校に挑戦してもいいですし、逆に安全校は10くらい下の偏差値帯まで視野に入れた方がいいでしょう。問題傾向や日程、地理など複数の要因がからんできますので、実際のスケジューリングは塾と相談しつつ、親が主導できめていくのがいいと思います。
偏差値なんて急にはあがらない
夏休みに頑張ったんだから秋には急激に偏差値が上がると思っている保護者は多いですが、そうはいきません。偏差値なんて急にあがりません。
夏休みに子どもがいくら頑張って勉強していても、まわりの子どもも本気で取り組み始めます。つまり全体があがるので、これからの時期は偏差値が上がりにくい時期なのです。この時期、塾では「偏差値が下がってなければそれは相当頑張っている証拠」とよくいいます。
基本的には夏は各教科の総復習というカリキュラムが組まれていて、秋口からだんだん過去問に取り組むようになっていきます。夏の終わりのこの時期に、まだ単元の復習が終わってなければ、あせらず基礎の見直しをしたほうがいいでしょう。苦手な教科があれば、そこをおさえていくのが常道です。
得意な教科を伸ばすのも大切ですが、得点源と考えると、苦手に取り組む方が確実に1点、2点をとっていけます。過去問をやっていくようになるとそれがとても大きな要素になります。合格最低点に1点足りなければ落ちるけど、1点上回れば合格するというシビアな世界です。
過去問を始めるようになると、偏差値なんてどうでもよくなってきます。模試というオールラウンドな仕組みのなかの相対的な順位でしかないからです。
これが入試直前の学校別模試になると、話がちょっと違ってきます。学校別模試はその学校に合わせた問題が出されますし、受験者もおおむね志望者です。学校別模試なら、順位を気にして、解き直しもしっかりやりましょう。
偏差値はある程度の目安にはなりますが、本当に絶対的な数値ではありません。受験直前になると、そこに気づきます。5年生の頃に塾のクラス分けや偏差値にこだわっていたのがうそのように気にならなくなります。
だから、今から模試を受ける際には、偏差値に一喜一憂せず、子どもが機嫌良く勉強できる環境作りをしていってあげてほしいです。